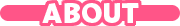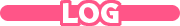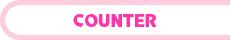穢翼のユースティアSS 素直になれない私の居場所

オーガストの新作穢翼のユースティア。
夏コミで頒布されたチラシを見ると、
もはや血は避けられない感もありますが果たして…?
世界観についてはだいぶ固まってきたように思いますが、
逆にヒロイン像については初報からほとんど追加されていないような?
公式に情報が出そろっていない今こそが創作活動のチャンス。
そんな話を聞いて、自分も突発的にSSを1本書き上げてしまいました。
というかSSなんて書いたのはこれが初めて。
ヒロイン像を考察してあれこれ論じるよりSSを書き上げた方が伝わりやすい?
そんな風に思って気がつけば何とか仕上がっていました。
自分でもビックリ。夏コミでテンション上がっていたんですかね。
とは言えいろいろツッコミどころ満載のSSですが、
初めてってことで大目に見てください…。
穢翼のユースティアSS 素直になれない私の居場所
「――はい、まあこんなところね」 余った包帯を片付けながら相手の顔も見ずに言い放つ。 「さんきゅー、エリス。一時はどうなるかと思ったよ」 「たかが捻挫で大げさなのよ。私だって暇じゃないんだけど?」 「とは言ってもこの身体に何かあったら、それこそ生きていけないんだもん。 そりゃちょっとは神経質にもなるってもんよ」 「だからっていちいち私のところに来ないでよね」 「まあまあ、ホントに感謝してるんだから。 仲間もみんな言ってるよ?エリスがいると何があっても安心だって」 「やめてよね、私が医者をやっているのはあくまで副業。 本業はカイムの――」 「あーはいはい、わかってるって。本業はカイムの妻、でしょ? もうイヤってほど聞いたよそのセリフ」 「わかってるなら尚更よ、私はカイムの世話で忙しいの」 「またまたぁ。エリスって家事はからっきしじゃな―― おっと何でもないよ。そんな怖い顔しないでってば。 それじゃあエリス、ホントありがと、また何かあったらよろしくね」 そう言うと、来たときと同じようにリサは慌ただしく帰っていった。 まったく、いつものことながらいい加減にしてほしいものだ。 リサは何かにつけて私のところにやって来る。 やれ料理中に指を切っただの、やれ街道で足をひねっただの。 ここ牢獄にいる以上、健康でいられることの方が珍しいくらいなのに 毎回小さなことでやって来ては、治療の傍ら世間話ばかり一方的に話していく。 彼女なりの生きがいなのかもしれないが、こちらはいい迷惑だ。 何も好きで医者をやっているわけではない。 ここ牢獄で生きていくためには何かしらに長ける腕が必要なのだ。 カイムの妻、と公言しているだけではダメなのは自分でもわかっている。 だからやりたくもない医者で生計を立てているのだ。 そんな風に考えると急にやる気がなくなってきた。 今日はもう店じまいを決め込んで薬草やら包帯やらを片付けていると、 ユースティアが買い出しから帰ってきた。 「ただいま戻りましたー」 「あら、ずいぶん遅かったじゃないの」 「はい、帰り道にばったりメルトさんにお会いして少し話し込んでしまいました。 それにほら見てください!メルトさんからこんなにお野菜をいただいちゃいました! 今日のお夕飯はポトフにしましょう!カイムさんも喜びますよ!」 メルトからもらったらしき紙袋に入った食材をのぞき込んで 笑顔で夕飯のプランを立てているユースティアを見て、 またいつもの対抗心が芽生えてしまう。 「ちょっと、いったい何度言ったらわかるのよ。 彼の世話は妻である私だけで十分。あなたが出る幕はないわよ」 「え?でもエリスさん、お料理は私が…」 「ほら、いいからどきなさい。ちょうど私が夕食の支度をするところだったのよ」 困惑気味のユースティアを押しのけるようにして厨房の前に立つ私。 正直料理は面倒くさい。 ただ、だからといって彼女にカイムの世話をさせるのはどうしても我慢ならないのだ。 彼女――ユースティアが来てからしばらく経つ。 彼女は憎らしいくらいによくできた子だった。 料理はおろか家事全般もそつなくこなす。 私とは正反対。 これが嫉妬だってことくらいわかってる。 本当は彼女に料理を任せた方がいいこともわかってる。 でも、どうしてもカイムの世話だけは私がやりたい。 だって、私は彼の妻なのだから。 そう決意すると、まるで親の敵を見るかのように厨房を一瞥して料理に取りかかった。 ユースティアは後ろでおろおろしながらしばらく私を止めようとしていたが、 私が無視し続けると、あきらめたのか静観することにしたようだった。 ほどなくして、できあがった料理を前にユースティアと私が向かい合う。 ユースティアは何か言いたそうに料理をちらちら見ていたが、 やがて私の目を見ておずおずと口を開いた。 「あ、あの…エリス、さん?」 「…何よ?」 「その…作っていただいたお料理なんですけど…」 「……」 「……」 また二人して黙ってしまう。 どれくらいそうしていただろうか。 再びユースティアが口を開く。 「…お料理、ちょっと焦げちゃいましたね」 「……」 無言で返す私。 彼女はそう言うが、実際はちょっとどころではない。 先ほどまで料理になるべく夢見ていた食材たちが見事に真っ黒だ。 もはや炭にしか見えない。 「……」 「……」 わかっている、私に家事の才能はないのだ。 カイムのためでなければこんな面倒なことなんてする気にもならない。 そんな態度で作られてたまるかとばかりに黒い物体はその存在を主張していた。 ユースティアは料理――になりそこねたその黒い物体をもう一度見ると、 やおら何かを決意したかのように真剣な顔になり、おもむろにエリスの手を取った。 「エリスさん!私と一緒にお夕飯の支度しませんか!?」 「…えっ?」 「一緒にお料理すれば一人で作るよりずっとずっとおいしいものが作れますよ!」 おもむろなユースティアの気迫にやや気圧されながら思う。 きっと、彼女なりの優しさなんだろう。 私に料理の才能がないのは誰が見ても明らか。 でも、そこには一切触れず一緒に料理をしようと言ってくれる。 私がやりますからとは決して言わず、みんなが笑顔になる方向を目指すように。 なんて健気な子なのだろう。 私がこうしてつらく当たっても決して嫌おうとしない。 それどころかうち解けようとさらに踏み込んでくる。 彼女の優しさに思わず首を縦に振りそうになる。 でも、わかっていても受け入れられなかった。 私自身のプライドがそれを許さなかった。 私はユースティアの手を払いのけるようにして言い放つ。 「もういいわ、夕食の支度はあなたがしてちょうだい。 私は夕食まで新薬の調合をしているから」 「…そう、ですか」 そう言ってしゅんとなるユースティア。 ここまでくるとさすがに罪悪感もこみ上げてくる。 そんな感情を悟られないように私は早々と自室に引きこもった。 ユースティアがいい子なのはわかっている。 彼女の表情はとても牢獄の住人とは思えないほどに明るい。 街を歩けばいろいろな人が声をかけてくれる。ちょっとした人気者だ。 誰かが言っていた、ティアちゃんは心のオアシスだ、と。 そんな彼女の優しさ、彼女の良さを知っているから思ってしまうのだ。 あの子が私からカイムを奪ってしまうんじゃないか、と。 私の心と身体はカイムのもの。 私からカイムを除いたら何も残らない。ただのがらんどうだ。 そんな私の立場を崩しかねないユースティアにどうしても嫉妬してしまう。 自分でも醜いことはわかっているのだが、彼女にはつらく当たってしまうのだ。 それでも彼女はめげずに私と一緒に笑おうとする。 そんなときふと思う。 そういえばしばらく心から笑えていない。 皮肉や嘲笑で笑うことは多くとも、楽しくて笑うことなんてあまりない。 ここ牢獄にいるのだから当たり前なのかもしれないが、 楽しさなんてほとんどないのだ。 それでも彼女はいつも笑っている。 彼女の笑顔はどこから来るんだろう? 私もあんな風に屈託なく笑うことができるんだろうか? どこまでもネガティブに落ちそうになる思考を打ち切るかのようにかぶりを振る。 大丈夫、カイムは私を捨てたりなんかしない。 ほどなくして、なにやらいい匂いが漂ってきた。 ユースティアの料理もまもなく完成なのだろう。 カイムもそろそろ帰ってくる頃だろうか。 「戻ったぞー」 そう思った矢先、カイムが帰ってきたようだ。 夫を迎えるのは妻の基本、これだけはユースティアに譲れない。 彼女の声がするよりも早く玄関でカイムを出迎える。 「お帰りなさい、カイム」 「ん」 二人が居間に向かうと、ちょうど料理ができあがったようで、 ユースティアはテーブルにお皿を並べていた。 「お帰りなさいカイムさん、すいません出迎えられなくて。 ちょうどお夕飯ができたところですから、座ってくださいね」 「お、グッドタイミングだな。いつも悪いな、ティア」 「いえいえ、お気になさらずに。お料理なら任せてください。 今日は特製ポトフですよ、メルトさんからお野菜たくさんいただいたので」 「メルトが?そうか、今度礼を言っておくか」 「はい、よろしくお願いしますね」 そう言いながら座ろうとしたカイムの動きがピタっと止まる。 「カイムさん、どうかされましたか?」 「いや、ちょっと待て。確認させてくれ」 「?」 「これは、ポトフだな。うん、旨そうじゃないか」 できたてなのか未だ白い湯気の立つ鍋を見て、カイムが納得する。 「だが…こっちの方は…」 もう一つのお皿に盛られた料理を見て顔をしかめる。 「おい、エリス?」 「…何よ?」 そっぽを向きながら私は応える。 「またおまえか…。 いつも言っているだろ、家のことはティアに任せておけって」 「いいじゃない、私だって料理くらいできるわよ」 「…ほう、おまえはこの黒い固まりを料理と言い張るんだな?」 「そうよ?ちゃんと火も通してあるし問題ないでしょ?」 これ以上言っても無駄と悟ったのか、カイムは盛大にため息をついた。 「おまえなぁ、そりゃ確かにここに住んでりゃ 相当アレなものでも食べていかないと生きていけないが だからって炭までは食えんだろ…」 「いいじゃない細かいことは。口に入れれば一緒よ」 「違うから言ってるんだよ…」 そんな私たちの様子を見て、ユースティアが間に入ってくる。 「まあまあカイムさん、エリスさんも一所懸命作ったんですよ。 今回はちょっと失敗しちゃいましたけど、次は大丈夫ですよ!ね、エリスさん?」 屈託のない笑顔でそう言われると、 先ほどこみ上げた罪悪感がまたも頭をもたげてくる。 「う…も、もちろん当然よ?」 「で、その大丈夫な次ってのはいつ来るんだよ…」 やるせないのかそう言って頭をかくカイム。 「……?」 ふと違和感を覚える。 どうもカイムの動きがおかしい。 彼の動かした右腕がほんのわずかだがぎこちない。 「ちょっとカイム、右腕、どうしたの?」 「ん?何のことだ?」 「とぼけないで。ちょっと見せてみなさい」 そういって無理矢理腕をまくり上げると案の定、二の腕に真新しい切り傷があった。 そう深くはなさそうだが、このままにすれば化膿してしまうかもしれない。 「ちょっとどうしたの、これ!?」 「なに、仕事でちょっと油断しただけさ、大したことはない」 「何言ってるの!化膿したらどうするのよ!?いいからちょっと来なさい!」 そういってカイムを無理矢理奥の自室に連れて行く。 カイムの言ったとおり、傷は浅く大事になることはなさそうだった。 だからといって放っておいてもいい怪我というわけではない。 傷口を丁寧に消毒し、薬草を練り込んだ軟膏を優しく塗っていく。 さすがにバツが悪いのか、カイムはエリスのされるがままになっていた。 「まったく…大変なのはわかるけど、もっと自分を大切にしてよね。 あなたがいなくなったら、私どうすればいいのよ」 「ん…すまんな。気をつけるよ」 「もう、また口ばっかり。何度も聞いたわよ、それ。 今度こそ本当に気をつけてよね?」 自分でも思う。リサのときとは大違いだな、と。 それはそうだ、私の持つ医者としての知識はすべてカイムのためのもの。 カイムの怪我は私の持てる全てをもって治したいと思う。 それが妻の役目、絶望しかけていた私を救ってくれた彼への恩返し。 そして何より、私はカイムの治療をするこの時間が好きなのだ。 彼を治療するこの空間は私の聖域。何人たりとも邪魔はできない。 この空間、時間にはあのユースティアですら立ち入ることはできない。 カイムと本当に二人きりの時間を過ごせる瞬間なのだ。 最後に傷口をいたわるように丁寧に包帯を巻いて治療を終える。 「はい、これでおしまい。 これで大丈夫だとは思うけど、念のためまた明日患部を診せてよね」 「ん、さんきゅーな、エリス。 やっぱ頼りになるなぁエリスは」 「!? もう、なに言ってるのよ!ほらさっさと夕食にしましょう」 頼りになるなんてことを言われ、赤くなりかけた顔を隠すかのように カイムの背中を押して居間に向かう。 居間に戻ると、そこにはニコニコ笑顔のユースティアが待っていた。 「なんだティア、ずいぶんとご機嫌だな。 俺が怪我したことがそんなにうれしいか? 「ええっ!?ち、違いますよぉ。 やっぱりお二人ってすごいなぁと思いまして」 「私たちが、すごい?」 「はい! だって、私なんてカイムさんのお怪我に全然気づけなかったのに、 エリスさんすぐに見抜いちゃったじゃないですか。 お料理のことでちょっとケンカしてても、よく見ているんだなぁって。 お二人ともお互いのこと何も言わなくてもわかっているみたいで すごいなぁって思ったんですよ」 「そうか…まあつきあいだけは無駄に長いからな」 「ちょっと、無駄ってどういうことよ?」 「あはは。ケンカするほど仲がいいって言うんですかね? なんだかちょっと羨ましいです」 照れ隠しに口をとがらせるカイムと私を、 ユースティアは本当に羨ましそうに眺めていた。 彼女の笑顔のおかげか、ほどよく和やかな雰囲気となり、 それからの夕食は久しぶりににぎやかなものだった。 彼女の振りまく笑顔が私たちにも伝播したようだった。 弾む会話の中、思う。 ユースティアは私からカイムを奪いかねない危険な子であるのには変わりない。 でも、彼女の持つその明るさや優しさには、 私自身もずいぶんと救われているのかもしれない。 ここ牢獄にいてもなお、笑顔を絶やさない彼女。 そんな笑顔を見ていると、ありもしない希望を抱いてしまう。 いつか私にも何の憂いもなく心から笑える時が来るんじゃないだろうか。 そんな未来を彼女が運んできてくれるんじゃないだろうか。 それは牢獄という現実から目を背けたただの妄想なのかもしれない。 でも、彼女の笑顔を見て思う。 そう信じてみるのも悪くないわね、と。
2010-08-18 (Wed) | COMMENT (0)
COMMENT